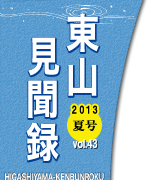おかぼという言葉をご存知でしょうか。南瓜をさす京言葉です。京都で南瓜といえば、冬至を思い浮かべる方も多いと思いますが、今回は夏のおかぼのお話。平安時代、山中で迷った高僧円珍が鹿に助けられたことから名付けられたという鹿ヶ谷の地には、京都ならではの形状をしたおかぼがありました。
京都の伝統的な京野菜のひとつ、鹿ヶ谷カボチャは、瓢箪型の形状で一度見ると忘れられないひょうきんな姿。現在一般的に食されている西洋南瓜とは別種の日本南瓜です。
「寺伝によると1790年頃の寛政年間に、粟田に住んでいた玉屋藤四郎が津軽に旅をした際に持ち帰った南瓜の種を、鹿ヶ谷の庄米兵衛に与えたのが起源。当地で栽培したところ、突然変異して瓢箪の形になったようです」。そうお話しいただいたのは安楽寺の伊藤副住職。安楽寺は、毎年7月25日に『鹿ヶ谷カボチャ供養』が行われることで知られるお寺です。その始まりは、病気が流行していた時世に、真空益随(しんくうえきずい)上人が本堂で人々を病苦から救おうと百日間の苦行を断行した際、ご本尊阿弥陀如来からの「夏の土用の頃に鹿ヶ谷カボチャを振る舞えば中風にならない」という霊告より。以降、鹿ヶ谷カボチャ供養は、220年以上も続く鹿ヶ谷にはなくてはならない行事となっています。
「毎年、檀家の皆さまのご協力で鹿ヶ谷カボチャを炊きあげ、供養にお越しいただいた方々に振る舞っています。最近では全国からお越しいただくようになり、200㎏以上の鹿ヶ谷カボチャの煮物が早々になくなってしまうことも」と副住職。実は鹿ヶ谷かぼちゃは、農地が減少したこの地で栽培されなくなって久しい京野菜。「毎年、200㎏を超える鹿ヶ谷カボチャを用意するのも、多くの協力者の力添えがあってこそ」と副住職は感慨深げに。
京都の伝統野菜と文化が密接に関わり合い、多くの檀徒の力により今に継承されてきた安楽寺の鹿ヶ谷カボチャ供養。今年も京のおかぼが、霊験あらたかなひとときを夏の京都にもたらします。
|
|

「この寺は、法然上人の弟子、住蓮と安楽が修行した地。二人の菩提を弔うため、この寺が建てられました。茅葺き屋根の山門をくぐると、春は躑躅、秋は紅葉に彩られます」。

鹿ヶ谷カボチャは、肉質が緻密で粘質があり、煮くずれしにくいのが特徴。果皮は熟すにしたがって深緑色からオレンジ色へ変わります。
|